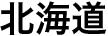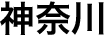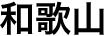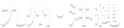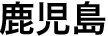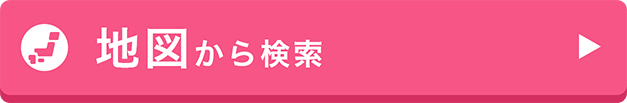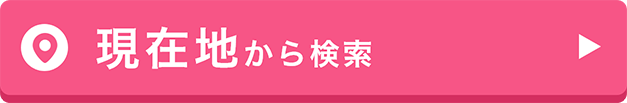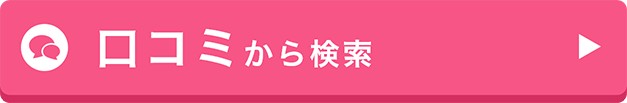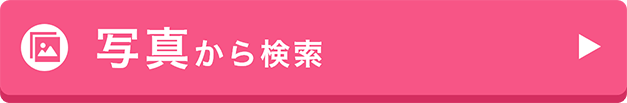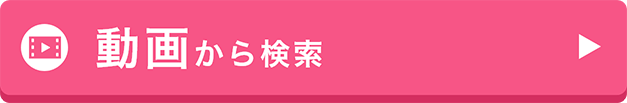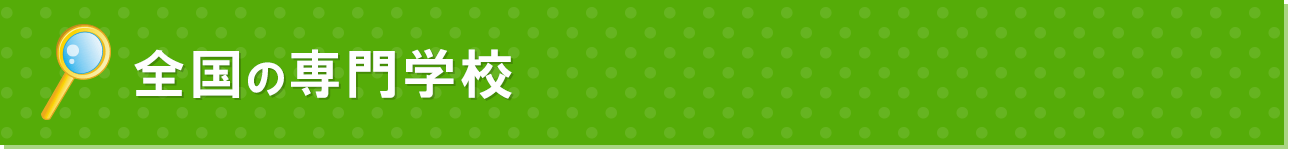 福祉専門学校
福祉専門学校
スタディピアは、日本全国の福祉専門学校を検索できる国内最大級の情報サイトです。卒業生やご近所の皆様からの基本情報や口コミ、投稿写真・動画などをリアルな声をチェックすることができるので、学校案内だけではわからない様々な情報を収集できます。
福祉専門学校とは
「福祉専門学校」についてご紹介します。福祉は、様々な人が幸せに自分らしく暮らせるよう、あらゆる手助けを行う仕事のこと。将来、福祉の分野で就職を目指している人は、どのような学校を選んでいるのでしょうか。
進学先を選ぶにあたり「自分のなりたい職業に近づける学びを提供してくれるのか」「卒業するだけで国家資格が取れるのか」「学費はどのくらい必要なのか」「受験方法はどうなっているのか」など、気になることはたくさんあります。
「福祉」と名前が付いていたり、福祉関係の学部・学科を設置していたり、福祉を学べる学校は様々です。本記事では、福祉専門学校について、国家資格の内容と取得方法、気になる学費、受験方法も合わせてご紹介します。
目次
- 1.福祉専門学校とは
- 1.1社会福祉士
- 1.2精神福祉保健士
- 1.3介護福祉士
- 2.福祉専門学校の勉強内容
- 2.1福祉専門学校のカリキュラム
- 2.2福祉専門学校の偏差値
- 3.福祉専門学校の学費とその他費用
- 4.福祉専門学校で取得できる資格
- 5.福祉専門学校の就職率と就職先
- 6.福祉専門学校の受験
- 7.福祉専門学校の選び方
- 8.福祉専門学校を探すには
- 9.福祉専門学校を探すなら「ホームメイト・リサーチ」で検索する
- 10.まとめ
福祉専門学校とは

福祉専門学校では、福祉・介護業界のスペシャリストを目指すことが可能です。福祉専門学校には、厚生労働省主管の国家資格である「社会福祉士」「精神保健福祉士」「介護福祉士」という通称「3福祉士」の養成課程が置かれています。
所定のカリキュラムを履修すると、資格試験を受験する権利を得ることができ、試験に合格すれば免許を付与されるのです。
福祉の仕事が求められる場面は様々。看護、リハビリテーション、保育、栄養管理など多岐にわたります。3福祉士以外にも、医療分野の「言語聴覚士」「作業療法士」「柔道整復師」「鍼灸師」、保育分野の「保育士」「幼稚園教諭」などの資格があり、学校のカリキュラムも多種多様。
広く福祉系の専門職を目指せるよう、学科・コースが職業ごとに設置されている総合的な専門学校から、特定の職業・資格に特化した福祉専門学校まで、学校の幅が広いのも特徴です。
社会福祉士
【社会福祉士の国家資格取得フロー(基礎科目+養成施設の場合)】
福祉系大学
または
専門学校
(4年)
福祉系短大
または
専門学校
(3年)
福祉系短大
または
専門学校
(2年)
児童福祉士、身体障害者福祉士などの
行政職4年
相談援助
実務1年
相談援助
実務2年
短期養成施設など(6ヵ月)
社会福祉士国家試験
社会福祉士資格取得(登録)
社会福祉士はソーシャルワーカーとも呼ばれ、日常生活において悩みを抱えている人を手助けするのが仕事。「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」によると、社会福祉士として登録しているのは全国で約25万人以上です。
社会福祉士の主な業務は、困難を抱えている人からの相談を受け、関係者との連絡・調整を行い、問題解決を図ること。身体的、あるいは精神的な障害や、環境上の問題など、サポートが必要な理由は幅広く、社会福祉士が勤務している場所も様々です。行政、福祉施設をはじめとして、学校、企業、社会福祉協議会など、活躍の場は多くあります。
福祉専門学校を経て社会福祉士になるには、どのような流れになっているのでしょうか。社会福祉士試験を受験するためには、福祉系の大学、短大、専門学校で必要な科目を履修することが必要です。
4年制の専門学校で社会福祉士を目指すと、卒業と同時に受験資格を得ることができます。2~3年修業の学校の場合は、卒業後、相談援助実務を1~2年経験しなければなりません。さらに養成施設への通学が課されることもあります。
また、児童福祉、身体障害者福祉などの実務を4年以上経験すれば、短期養成施設などで6ヵ月修業することで受験資格を得ることが可能。
一般の学校を卒業した場合は、大学に応じた年数だけ相談援助実務を経験した上、一般養成施設で1年以上の就業が必要です。相談援助実務を4年以上経験すると、一般養成施設に1年以上通うことで受験することができます。
一部の専門学校では、夜間に開講している学科・コース、通信課程を開設。そのため、社会人になってからでも社会福祉士を目指すことが可能です。
参考URL:厚生労働省 社会福祉士の概要について
精神福祉保健士
【精神福祉保健士の国家資格取得フロー(基礎科目+養成施設の場合)】
福祉系大学
または
専門学校
(4年)
福祉系短大・専門学校など(3年)
福祉系短大・専門学校など(2年)
児童福祉士、身体障害者福祉士などの
行政職4年
相談援助
実務1年
相談援助
実務2年
短期養成施設など(6ヵ月)
精神保健福祉士国家試験
精神保健福祉士資格取得(登録)
精神保健福祉士は「精神保健福祉士法」で定められている国家資格です。社会福祉士と同様にソーシャルワーカーと呼ばれていますが、精神保健福祉士は、精神的な障害・病気を抱えている人の手助けを担当。社会復帰に関する相談への対応、日常生活への適応へのリハビリなどをサポートするため、病院・生活支援施設などの医療系施設での勤務がほとんどです。
精神保健福祉士を目指している高校生は、福祉系学校の中でも4年制の保健福祉系大学または専門学校に入学すると、卒業後に国家試験の受験資格を得られます。
2~3年の修業期間の場合は、在学中に指定科目を履修し、卒業後は修業期間に応じた年数の相談援助実務に従事しなければなりません。また、福祉専門学校卒業者・社会福祉士登録者は、受験資格を得るために短期養成施設で半年間学ぶ必要があります。
一般の大学・短大を卒業したあとに精神保健福祉士を目指す場合、4年制大学なら一般養成施設等で1年以上修業すれば受験資格を得ることが可能。しかし、2~3年制大学の場合、1~2年間相談援助実務を経験し、さらに一般養成施設等での修業が必要となります。また相談援助実務を4年経験すると、一般養成施設等に1年以上就業することで受験可能です。
社会人になってから精神保健福祉士を目指す人のため、一部の専門学校では夜間コースを設置。一般養成施設と呼ばれる学校では、通信教育などで卒業することも可能となっています。
参考URL:厚生労働省 精神保健福祉士について
介護福祉士
【介護福祉士の国家資格取得フロー】
実務経験3年以上
+
実務者研修修了者
福祉系高校
高校卒業後、
福祉士養成施設に指定された福祉専門学校(2年以上)
介護福祉士国家試験
介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士は、お年寄り、身体の不自由な人を助ける、介護のエキスパート。仕事は主に「①食事、入浴、車いすなどでの移動など、生活にかかわる動作の介助」「②本人、関係者からの介護に関する相談に対しての助言」「③家事・身の回りの世話など、生活の支援」の3つです。
特別養護老人ホーム、身体障害者施設などの社会福祉施設で介護業務を行う以外にも、ホームヘルパー、医療系施設での相談員など、活躍の場は多岐に亘ります。
国家試験に合格し、介護福祉士になるにはどうすれば良いのでしょうか。1番の近道は、高校卒業後、介護福祉士養成施設に指定された福祉専門学校に入学すること。
2年以上修業し、介護の専門知識を身に付ければ、卒業後に介護福祉士試験を受験できます。また福祉系大学・社会福祉士養成施設、保育士養成施設などを卒業した場合、介護福祉士養成施設で1年以上学ぶことで、受験が可能です。
養成施設などで修業し受験資格を得て、筆記試験に合格することが資格取得の最短ルート。ただし、2017年度(平成29年)~2026年度(令和8年度)までの卒業者は、筆記試験合格を経ずに、期限付きで介護福祉士の資格取得が可能です。その後、実務経験を5年間勤続で積むことで、正式な介護福祉士として登録されます。
なお「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、2027年度(令和9年度)以降に卒業する場合は、筆記試験に合格することが必須条件。
夜間部の学科・コースで学び、社会人として働きながら介護福祉士を目指すことはできますが、実技を身に付けることが必要となる職業なので、通信教育は認められていません。
参考URL:厚生労働省 介護福祉士の概要について
福祉専門学校の勉強内容

福祉専門学校では、どのようなことを勉強するのでしょうか。所属する学科・コースによって内容は変わりますが、目指す職業の専門的な知識が中心です。
福祉専門学校のカリキュラム
社会福祉士を目指すコースでは、資格取得に必要な指定科目を中心として、ソーシャルワークの基礎から医学、社会学に至るまで、将来仕事をする上で役立つ様々な知識を習得。
精神保健福祉士には、精神医学、精神科リハビリテーションなどの精神疾患の知識が不可欠です。また、介護福祉士は、介護の基礎知識からコミュニケーション、心と身体のしくみなどを学び、痰(たん)の吸入など医療的ケアの習得も目指します。
福祉専門学校の授業では、実習が多いのが特徴。より現場を理解し、すぐに活躍できる人材を育てることが求められているからです。国家試験の受験サポート、各種資格試験の対策を行っている学校もあります。
福祉専門学校の偏差値
福祉専門学校の受験を考える際には、偏差値が気になるかもしれません。偏差値とは、同じ試験を受けた人の中での平均を50とし、全体で自分がどのくらいの成績かを表す指標。
専門学校入試の場合、模擬試験は看護学校など医療系の学校を除き、ほとんど実施されません。各学校の入試方法・必須科目が異なるのがその理由です。
専門学校は、特定の分野の専門的な内容を学び、即戦力を養うことを第一としていることから、面接、小論文を重視する傾向があります。そのため、志望校に応じた対策が重要です。
福祉専門学校の学費とその他費用
一般的に専門学校に合格すると「入学金」と初年度の「授業料」「実習費」などの費用を入学までに納入。ある年の日本政策金融公庫の調査によると、専門学校入学から卒業までに必要な学費の平均は、300万円超。内訳は、入学金が約60万円、授業料が約260万円です。
福祉専門学校では、実習が欠かせません。学校・カリキュラムによって異なりますが、実習費、施設設備費、さらに資格検定費、教育教材演習費などが必要です。
学費としてまとまった金額が必要となるため、金銭面から進学をためらってしまう人もいるでしょう。そこでチェックしておきたいのが、学びたい意欲のある人の学費をサポートする制度が整っているかどうかです。
優秀な成績で入学する学生に対して、学費の一部免除などを行う特待生制度をはじめ、各種奨学金、修業資金援助、教育ローン、学費分納制度など、様々な方法で支援を行っている学校があるので、確認しておきましょう。
福祉専門学校で取得できる資格
福祉に携わる仕事は幅広く、福祉専門学校では、3福祉士をはじめ様々な国家資格を得るコースがあります。
目指すことができる国家資格は、心理に関する相談・助言を行う「公認心理士」、乳児・幼児の保育を行う「保育士」、幼稚園で未就学児の指導を行う「幼稚園教諭」、リハビリテーションの支援を行う「作業療法士」、言葉・聞こえに悩みを持つ人のサポートをする「言語聴覚士」など。いずれも、専門の課程を履修し、指定の科目・実習が不可欠です。
様々な仕事に便利な資格は他にも、心の悩みを持つ人に寄りそう「心理カウンセラー」、認知症に対する正しい知識と理解を持つ「認知症ケアサポーター」、住みやすい住環境を提案する「福祉住環境コーディネーター」、障害者のスポーツ参加のきっかけ作りを行う「初級障がい者スポーツ指導員」などがあります。これらの資格取得を目指せる学校もあり、学校の特色のひとつです。
福祉専門学校の就職率と就職先

福祉専門学校の卒業生は、どのような進路を選び、どこで活躍しているのでしょうか。気になる就職率と就職先についてご紹介します。
専修学校(専門課程)全体の就職率は、例年95%以上と高い数値で推移。多くの実習を積んでいる専門学校卒業生は即戦力となるため、福祉業界が求める人材に合致していることが背景にあると考えられます。
また、各学校では、学生の就職活動をサポート。企業からの求人票の取り扱い、セミナー、エントリーシート、面接のアドバイスを行うコーナーがあり、就職課・就職サポートセンターなど、名称は様々です。
就職先は専門性を活かす職場が多く、福祉の手を必要とする人を支える施設や企業で活躍可能。具体的には「障害者支援施設」「医療機関」「特別養護老人ホームなどの高齢者向け施設」「地方自治体など行政」「学校」「児童養護施設」「就労継続支援事業所」「地域包括支援センター」などです。
福祉専門学校の受験
福祉専門学校の受験方法は、大きく分けて以下の4種類があります。
| 入試方法 | 対象者 | 試験科目 |
|---|---|---|
| 一般入試 | 高等学校等を卒業、または卒業見込みの人 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した人 |
書類選考 学科試験または 作文 面接試験 |
| 推薦入試 | 高等学校からの推薦を受けられ、単願で受験する人(高等学校の推薦基準に準ずる) | 書類選考 面接試験 |
| AO入試 | 学校が発行したAO入試出願許可証を持っていて、単願で受験する人 | 書類選考 学科試験または 作文 面接試験 |
| 社会人入試 | 高校既卒者(ならびにそれに準ずる者)で、社会人(アルバイト・パートを含む)、または大学・短期大学・専門学校等に在学している人 |
一般入試は、進路をじっくり考え、他の学校・コースと併願する人におすすめです。推薦入試は、学校生活の経験、実績、入学後の学習意欲が重視されます。AO入試は総合型選抜と呼ばれ、受験校の求める学生像に合っているかどうかが判断基準。社会人入試は、各学校によって対象者が異なり、社会人経験・実務経験を問われない場合もあります。
福祉専門学校の選び方
福祉専門学校を選ぶ際に注目したいポイントは「希望している業種に特化しているかどうか」「学ぶ期間と時間帯」「資格の合格率」「就職率と就職先」の4つです。
自分の目指す職業に近づくためにも、カリキュラムは重要。専門学校には1~4年制があり、夜間コースもあります。より早く現場へ出たいのか、様々な科目を学びたいのか、よく考えて選びましょう。
合格率の高い学校は資格取得支援が充実。福祉業界の人脈が広い学校は、紹介できる就職先が豊富です。就職活動でも手厚いサポートを期待できます。
福祉専門学校を探すには
では、福祉専門学校を探すには、どのような手段があるのでしょうか。代表的な手段は「パンフレットなどの資料請求をする」「オープンキャンパスに行く」「高校生の場合、通っている学校の進路室、先生に相談する」「友人・知人から情報を得る」「インターネットで調べる」の5つです。
インターネットで検索するメリットは、各専門学校の特徴を比較しやすく、各専門学校の公式ウェブサイトなどから新しい情報を得られること。なかには入学後の雰囲気を感じられる動画を公開している学校もあります。
福祉専門学校を探すなら「ホームメイト・リサーチ」で検索する
施設検索「ホームメイト・リサーチ」のスタディピアでも、以下のような検索方法で「福祉専門学校」の情報を得ることが可能。検索方法は、以下の6種類です。
- 地域別に検索
- 施設名を入力して検索
- 地図から検索
- 口コミから検索
- 写真(動画)から検索
- カテゴリから検索
※モバイル端末では現在地から検索もあります
なお、おすすめの検索方法は「カテゴリ検索」です。「スタディピア」のトップページから、「福祉専門学校」を選択すると、全国の福祉専門学校を簡単に探すことができます。
まとめ
福祉専門学校では、豊富な実習と専門性の高い授業を受けることができます。福祉専門学校は、厚生労働省主管の国家資格「社会福祉士」「精神保健福祉士」「介護福祉士」の養成課程を設置。専門学校入学から卒業までに必要な学費の平均は、300万円超です。
また、福祉専門学校の入試方法には「一般入試」「推薦入試」「AO入試」「社会人入試」の4種類があります。
社会福祉分野のプロフェッショナルを最短ルートで目指せる福祉専門学校を、進学先として検討してみてはいかがでしょうか。自分が活躍している姿を思い描いて、夢を実現できる学校を探すなら、ホームメイト・リサーチがおすすめです。
専門学校の基本情報・知識
福祉のブログ情報
以下の都道府県をクリックして専門学校を検索してください。
関連情報リンク集
専門学校に関連する省庁サイトです。
法律や制度の確認、統計データの取得など、情報収集にご利用ください。
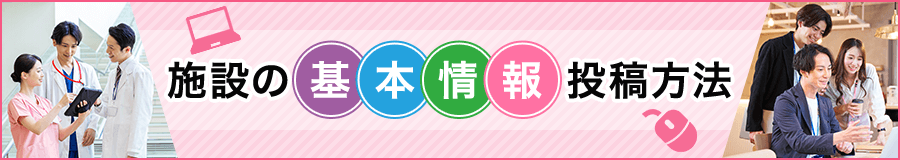
投稿をお待ちしております。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本