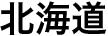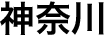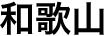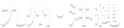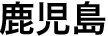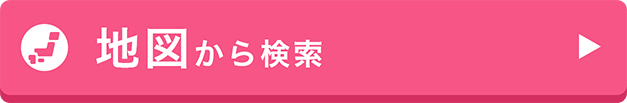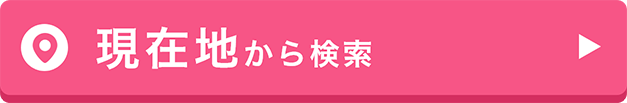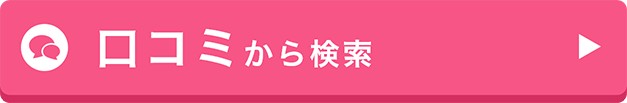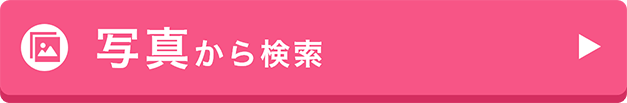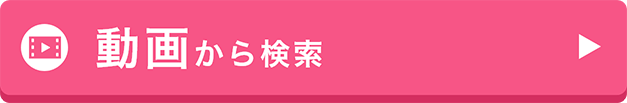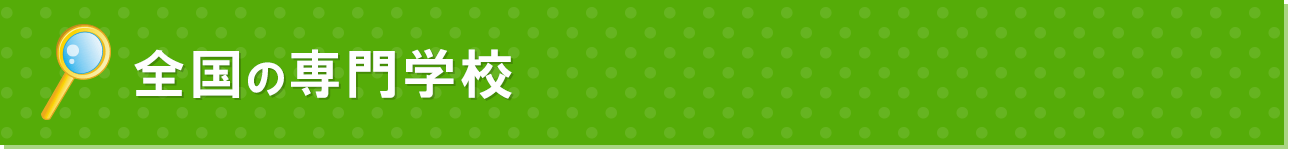 眼鏡専門学校
眼鏡専門学校
スタディピアは、日本全国の眼鏡専門学校を検索できる国内最大級の情報サイトです。卒業生やご近所の皆様からの基本情報や口コミ、投稿写真・動画などをリアルな声をチェックすることができるので、学校案内だけではわからない様々な情報を収集できます。
眼鏡専門学校とは
「眼鏡専門学校」についてご紹介します。これまで、眼鏡の販売員になるために必ず取得しなければならない資格はありませんでした。また2022年(令和4年)3月末までは「認定眼鏡士」資格がありましたが、これは民間検定。多くの眼鏡販売店では、社内で研修を実施し、一定のレベルに達した人を販売員としてきました。
そうした中で、2022年(令和4年)4月に国家資格「眼鏡作製技能士」が新設。今後は、眼鏡作製技能士である販売員が活躍し、眼科専門医と連携を取りながら、人々の目の健康を守っていくと期待されています。
眼鏡作製技能士になるための第一歩は、厚生労働省が定めた受験資格をクリアすることです。そのための学びをサポートしてくれる「眼鏡専門学校」について詳しく解説します。
目次
眼鏡専門学校の概要

高齢者の増加、スマートフォン・タブレットなどのデジタル機器の普及により、視力に悩みを抱える人が急増。その悩みは多様化・高度化しており、眼鏡に求められる役割は大きくなっています。
こうした背景から、眼鏡の作製には専門的な知識とスキルを持つ人材が必要だと考えられ、国家資格「眼鏡作製技能士」制度が新設されました。
「眼鏡専門学校」には眼鏡作製技能士の養成課程があり、受験資格が得られます。主に、高校卒業以上の学生のためのコース、4年制大学・短期大学・専修学校を卒業した学生のためのコース、すでに現場で働いている人のためのコースがあり、それぞれのレベルに合わせて学ぶことが可能です。
お客様とコミュニケーションを取ったり、ファッション面でのアドバイスをしたりすることも眼鏡製作の過程のひとつ。そのため、サービス・接客、色彩などにかかわる資格取得に力を入れている学校もあります。
眼鏡専門学校の数は決して多くはありません。その分、それぞれの学校には特色があります。例えば、眼鏡のエキスパートの輩出に特化している学校、眼鏡のファッション性にも着目した授業づくりをしている学校、企業との連携を活用している学校などです。
眼鏡専門学校の種類
眼鏡は医療機器であるため、専門性が求められます。眼鏡専門学校では眼鏡作製のスキルをひとつひとつ丁寧に高めていきます。
眼鏡作製技能士の資格は1級と2級に区分。それぞれの級には、以下のような違いがあります。
- ・1級:お客様に最適な眼鏡を提案できる。他の眼鏡作製従事者への指導、眼科専門医との連携も可能。
- ・2級:お客様に最適な眼鏡を提案できる。販売現場で働くための基礎の能力となる。
また、眼鏡専門学校では、眼鏡作製技能士の受験資格を得るためのカリキュラムが組まれています。ほとんどの眼鏡専門学校が2~3年制ですが、なかには通信教育で学ぶことも可能です。
| 2年制 | 3年制 | 通信教育 | |
|---|---|---|---|
| 学習内容 | 1年次:専門科目 2年次:実習、専門的な技術 |
1年次:一般教養 2年次:専門的な 講義 3年次:専門的な 技術 |
眼鏡販売店で即戦力となる加工技術、視力測定能力、フィッティング技術 |
| 卒業時に 得られる資格 |
眼鏡作製技能1級の受験資格 | 眼鏡作製技能1級の受験資格 | 眼鏡作製技能士1級または2級の受験 資格 |
| 特徴 | 4年制大学・短期大学・専修学校卒業者が入学 | 高校卒業者が入学 | すでに眼鏡関連会社に勤務している人も学べる |
| デメリット | 2年間で凝縮して学ぶため、その分1年分の授業料が多くかかる傾向 | 時間をかけて学べるため、入学希望者が多く、倍率が高い | メールで質問できるなどのサポートがないと、講義の理解が不十分になる |
※学習内容に関しては、学校によって異なる可能性があります。
眼鏡専門学校は、眼鏡のエキスパートの輩出に特化しているだけではありません。企業と密に連携していたり、支援を受けたりしている学校では、実習・インターンシップが充実しています。
眼鏡専門学校の勉強内容

眼鏡作製技能士の学科試験の科目には、「視機能系」「光学系」「商品系」「眼鏡販売系」「加工作製系」「フィッティング系」「企業倫理・コンプライアンス」など。また実技試験では、「視力の測定」「フィッティング」「レンズ加工」が行われます。
眼鏡専門学校では、これらの試験科目に対応。例えば「視機能系」では、「視力・屈折測定」が扱われ、光の屈折と近視・遠視・乱視の関係性などを学びます。
眼鏡作製技能士には、一人ひとりに適した眼鏡を作るだけではありません。眼科医による適切な診断・治療が受けられるように医療機関と連携していくことも求められており、最終学年で眼科での研修を実施する学校もあります。
検査・診察の様子を見ることができる他、検査機器を目の前にして、説明を受けられたりもするため、非常に学びの多い時間になるでしょう。また、眼鏡販売店、フレーム・レンズ工場の見学を行う学校もあります。
眼鏡へのニーズを聞き出したり、確実に測定をするためにコミュニケーションを取ったり、正しい取り扱い方法を説明したりすることも眼鏡作製技能士に必要な能力です。ロールプレイングで接客のトレーニングをしたり、ビジネスマナーを身に付けたりすることも積極的に行われます。
眼鏡専門学校の偏差値
他の専門学校と同じで、眼鏡専門学校にも偏差値という基準は設けられていません。眼鏡に関連する仕事に就きたい学生を広く受け入れており、資格取得ができる人材を社会に送り出すために、限られた時間で専門的な授業が多数。
授業をしっかりと理解していくために、学習意欲・基礎学力は欠かせません。また、どの学校も募集人数は多くないため、倍率は高くなっていくと考えられます。受験での作文・面接に備えるため、学生時代には自分の強みになるような経験を積むことも大切です。
眼鏡専門学校の学費とその他の費用
1年次には、80~130万円程度の学費が必要。その他には、教科書・工具代3~4万円程度です。2年次以降の学費は、80~100万円ほどになります。
他の専門学校と比較すると、眼鏡専門学校の学費は決して安くはありません。ただ、国家資格取得の道が開けることを考えれば、価値のある授業料と言えるでしょう。
また、どの学校も、校内に専門家がいない場合はスペシャリストを外部から招いて講義をしてもらったり、専門性の高い機材を豊富に導入したりと、授業を充実させて学生への還元に努めています。なお、通信教育の学費は30万円程度が相場です。
眼鏡専門学校の就職率と就職先

多くの眼鏡専門学校では、眼鏡関連の企業と連携・支援の関係性を築き、学生の就職活動を強力にバックアップ。就職先には、眼鏡販売店、コンタクトレンズ販売店、眼科、眼鏡のレンズ・フレームのメーカー、医療機器系のメーカーなどがあります。
認定眼鏡士資格が主流だったときには、7~8割の学生は眼鏡の販売店に就職していました。なお、眼鏡作製技能士は新しい国家資格であるため、さらに活躍の場が広がっていくと考えられます。
眼鏡専門学校の受験
眼鏡専門学校で学ぶ内容は、文系よりも理系に寄っているため、「文系の自分が受験をするのは難しいのでは?」と思う学生も少なくはありません。
しかし、眼鏡作製技能士は新しい国家資格であるため、新しい学問の分野とも言え、誰にとってもゼロからのスタート。文系・理系を問わず基礎から学べるカリキュラムが作られるため、安心して受験をすることができます。
受験はほとんどの場合、「一般入試」「AO入試」「推薦入試」「社会人入試」から選ぶことが可能です。
| 対象者 | 試験科目 | |
|---|---|---|
| 一般入試 | 高校卒業・卒業見込み 高卒認定試験合格者 |
書類選考、作文、面接、筆記試験、適性検査 |
| AO入試 | 書類選考、面接 | |
| 推薦入試 | 高校卒業見込みで、学校の推薦を受けた方 | 書類選考、作文、面接 |
| 社会人入試 | 通信教育の受講を希望する者 | 書類選考 |
AO入試では、高校3年生の5月あたりに行われるオープンキャンパスまたは学校説明会に参加をしてAOエントリー資格を得る必要があります。早い段階から情報をチェックし、行動していきましょう。
また、認定眼鏡士資格を持っている方には特例措置があり、眼鏡専門学校に入学せずとも、特例講習を受講し、講習後の修了試験を受けることが可能です。認定眼鏡士資格を持っていないものの、企業内の研修・検定を受けてきた方は、眼鏡専門学校の通信教育を受講すれば、眼鏡作製技能士2級の受験資格が得られます。
眼鏡専門学校の選び方
学校選びは「できるだけ自宅から近い場所にある学校にする」「企業との連携が強く、就職に有利な学校がいい」など、具体的に希望・目標を考えてみることが非常に重要です。
「①修業年数が2年以上」「②総授業時数が1,700時間(62単位)以上」「③試験などでの成績評価によって課程修了の認定を行っている」など3つの要件を満たすことで、卒業時には、文部科学省認定の称号「専門士」が得られる学校もあります。
「専門士」が付与されると、大学への編入が可能。将来の選択肢を広げることができるため、要件を満たした学校かどうかも調べてみると良いでしょう。
医療・福祉系の大学にも、眼鏡作製技能士の養成コースが設置されています。希望に合う専門学校が見つからない場合、大学の情報を集めてみるのもひとつの方法です。
また、眼鏡の関連企業が支援をする「企業奨学金」制度などを設けていることもあります。学費面での支援の有無も学校選びでは重要なので、積極的に情報収集をすることもおすすめです。
眼鏡専門学校の探し方
眼鏡専門学校は決して数が多くないため、高校生の場合、学校では十分な情報が得られないことも考えられます。インターネットで検索をするなどして、自分で学校の情報を見つける努力も必要です。
近くに眼鏡専門学校がある場合は、同じ高校から進学した人がいて、紹介をしてもらえるかもしれません。通ってみないと分からない学校の内側を知るチャンスなので、相談してみましょう。
なお、「眼鏡作製技能士」は非常に新しい資格であるため、専門学校のホームページには最低限の情報しか掲載されていない場合があります。資料請求をして、細かいカリキュラム、学校の特色をチェックすることが大切です。
眼鏡専門学校を探すなら「ホームメイト・リサーチ」で検索する
施設検索「ホームメイト・リサーチ」のスタディピアでも、以下のような検索方法で「眼鏡専門学校」の情報を得ることが可能。検索方法は、以下の6種類です。
- 地域別に検索
- 施設名を入力して検索
- 地図から検索
- 口コミから検索
- 写真(動画)から検索
- カテゴリから検索
※モバイル端末では現在地から検索もあります
なお、おすすめの検索方法は「カテゴリ検索」です。「スタディピア」のトップページから、「眼鏡専門学校」を選択すると、全国の眼鏡専門学校を簡単に探すことができます。
まとめ
眼鏡作製技能士は新しい国家資格。眼鏡に関連する仕事に就きたい学生にとって技能士資格の取得は、重要な目標となります。まずは眼鏡専門学校の情報を集め、自分に合った環境を見つけましょう。また、これからも眼鏡専門学校には、様々なコースが新設される可能性もあります。新たな情報にアンテナを張ることも大切です。
専門学校の基本情報・知識
眼鏡のブログ情報
以下の都道府県をクリックして専門学校を検索してください。
関連情報リンク集
専門学校に関連する省庁サイトです。
法律や制度の確認、統計データの取得など、情報収集にご利用ください。
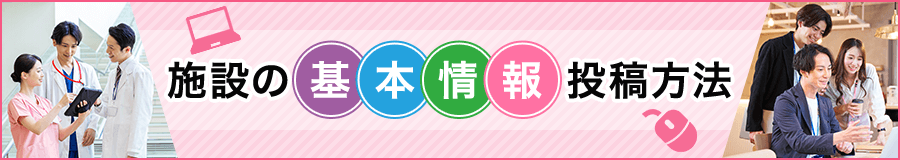
投稿をお待ちしております。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本