冬の専門学校情報
冬選考あり!建築士を目指している人におすすめしたい専門学校/ホームメイト
一級建築士を目指す高校生は必見です。大卒「学士」同等資格が取れる建築専門学校や、伝統のある有名校、一級建築士資格の合格率が高い実績校の情報までを網羅。まだ間に合う、冬選考のある専門学校もご紹介します。
受験前に知っておきたい!大卒「学士」同等資格が取得できる専門学校!

「建築士」になりたいのなら、憧れるのが「一級建築士」という国家資格の取得。とても狭き門で、受験資格でさえ、建築士法第14 条に基づき「学歴要件」など厳しく規定されています。大学を卒業した人は実務経験2年以上、3年制の短大卒業ならば3年以上、2年制の短大、高等専門学校、専門学校卒業ならば、4年以上の実務経験が必要というように。
ところが、何と専門学校でも、大卒「学士」と同等の資格が取得でき、「一級建築士」受験資格の実務経験が4年ではなく2年となるところがあるのです。それは、「高度専門士」課程のある専門学校。
「高度専門士」とは、文部科学省が認めた修業年限が4年以上等の要件を満たした専門学校の修了者に与えられる称号です。「高度専門士」の称号が付与された人は、大卒と同等以上の学力があると認められ、大学院の入学資格も与えられます。
また、社会人の場合は「職業実践専門課程」がある専門学校を選べば「教育訓練給付金」の対象校になっているので、最大で費用の60%(年間上限48万円)を給付してもらえる点も魅力。
将来の目標がはっきり決まっているのなら、この「高度専門士課程」、「職業実践専門課程」がある専門学校を選ばない理由はありません。「高度専門士」の称号を付与する専門学校名は、文部科学省のHPに掲載されていますので、しっかりと確認しましょう。
冬からでも間に合う、首都圏の建築専門学校探し
学校説明会やオープンキャンパスは、学校の様子や授業の雰囲気などを知るための大切なイベントです。1925年 (大正14年)に設立した長い歴史を持つ神奈川県横浜市にある「浅野工学専門学校」は、「高度専門士」の称号を付与する専門学校です。公共施設やビル建設に携わる人材を育成する「建築工学科」と、製図・デザイン・インテリアなどを学ぶ「建築デザイン科」の2つからなり、1人ひとりに即した指導で即戦力を身に付けていきます。ほぼ毎月1回、学校説明会を実施。施設見学や個別での相談会、在校生に直接話を聞くことも可能です。また、首都圏からの通学に便利な東京都北区王子本町にある「中央工学校」。体験入学は毎月開催されています。実際に授業を体験することで、学校の雰囲気を直に感じることができるのが魅力です。建築系の学びは「建築系学科」、「デザイン系学科」、「土木・測量・造園系学科」、「機械・CAD系学科」等で、自分の興味に応じて選択できます。
そして、「職業実践専門課程」がある学校としては、「青山製図専門学校」。昼間部と夜間部があり、どちらの体験入学も可能です。「建築学部」と「インテリア学部」からなり、さらに細かい学科に分かれています。保護者も同伴して学びの雰囲気を体験できる他、説明会と合わせて、模擬授業を見学することも。また、「大阪工業技術専門学校」は、「建築学科」、「設備環境デザイン学科」、「大工技能学科」、「インテリアデザイン学科」、「ロボット・機械学科」、「建築設計学科」があり、遠方からオープンキャンパスに参加する人には、宿泊費無料の体験宿泊サービスを実施。これらの学校は、一般入試が10~3月にかけて行なわれます。
一級建築士試験の合格人数が多い建築専門学校
難関資格である一級建築士試験への合格。これを目的として建築専門学校への進学を希望している人にとって、学校を決める際に気になるのが、一級建築士の合格率の高さです。
一級建築士試験は「学科の試験」と「設計製図の試験」が行なわれますが、「学科の試験」に合格しない限りその先には進めない、難関な試験。建築技術教育普及センターの発表によると、2016年(平成28年)の学科試験受験者は、26,096人。この内、学科試験合格者は4,213人。さらに製図試験合格者は3,673人でした。総合合格率は12%という競争率の激しさ。こちらでは、学校別合格人数も発表されています。全国にある建築専門学校の中で、合格率の高い専門学校を見ていきましょう。先ほどご紹介した「中央工学校」は、2016(平成28年 )の一級建築士試験の合格人数は24人。これは専門学校の中で1番の合格人数です。 次いで「大阪工業技術専門学校」は合格人数18人。全国の大学とくらべても引けを取らない数字です。一級建築士を目指す人は、合格実績も考慮の上、専門学校を選ぶのもおすすめ。



専門学校への入学を目指す人や、専門学校に在籍して進級を目指す人、さらには専門学校の卒業を控える人。専門学校にまつわるあらゆる立場の学生、生徒にとって冬は勝負の時期であり、春に向けて大事な準備の時期となります。入学したい専門学校がある方は、校風や教育方針がそれぞれ違いますので、冬の季節にしっかりと目指す学校の環境を把握しておくのが望ましいと言えます。
専門学校の学生寮
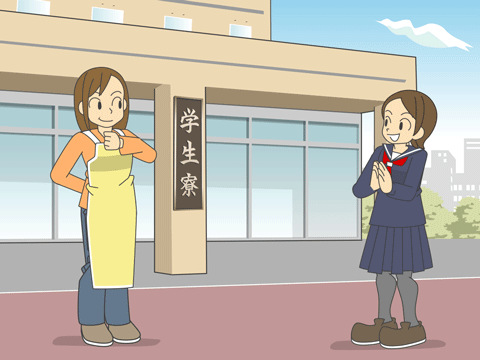
合格が決まり、4月からの専門学校生活に向けて、準備が慌ただしくなる冬。専門性の高い専門学校では、その分野を学びたいと地元以外の遠方から志願する人も大勢います。そのため、学生寮を完備している学校や、民営の賃貸アパートと提携して学生に割安な賃料で貸し出しているケースも多いのでチェックしてみましょう。学校によっては、ひとり暮らしに必要な家電や家具、空調機器などの設備を整えている場合や、栄養管理を徹底するために食事が付く寮などもあります。
学校までの通学の便はもちろん、最寄りの駅やスーパー、病院、銀行までのアクセスの良さなど、勉強に思う存分打ち込める環境は学校選びの際の決め手となるポイントです。住みやすい環境を整えているか否かは専門学校選びの際に重要ですので、資料を取り寄せたり、問合せをしたりしてしっかりと把握しましょう。
特に女子学生にとって気がかりなのが、防犯対策です。周辺の生活環境に配慮した立地や、24時間のセキュリティシステム、また寮母さんが常駐しているなど、女子学生でも安心して暮らせる点も、学生寮の魅力です。
さらに、寮生活のメリットは、同級生や先輩、後輩とのつながりが強固になること。親元を離れて心細さを抱いている仲間同士で共に助け合い、励まし合いながら学問に打ち込むことができます。
専門学校によっては、遠方の受験生と保護者が学校見学と合わせて、学生寮や周辺環境をチェックできるように、バスツアーなどを実施しているケースもありますので、参加してみるのも良いでしょう。
海外研修
専門学校で学ぶ分野について、本場や最先端の地を訪れ、実際に目で見て耳で聞き、体験することは、将来への夢を広げる大きなきっかけとなります。専門学校では、各国の提携校での研修を中心とした海外研修を実施する学校も多々あり、中には1年次の冬に数週間から1ヵ月程度の海外研修を行なっている学校もあります。期間や時期、渡航先は学ぶ分野や学校によって様々です。
例えば製菓の専門学校では、フランスやドイツ、ベルギーなどヨーロッパを周遊して菓子やパンの伝統に触れる機会を設けたり、美容の専門学校では海外のセンスや最先端のテクニック、トレンドを体感するためにイギリスのロンドンやフランスのパリなどを訪れたりします。ホテルやブライダル、観光業界などのサービス業を目指す学校では、アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアなどへ英語の語学研修をかねて訪れることもあります。
もちろん、数ヵ月単位や1年間など長期の留学プログラムを用意している学校もありますので、海外での学習に興味がある場合は学校へ問合せてみましょう。
進級試験
専門学校に通う学生にとって、毎年の気がかりなことと言えば進級試験です。多くの学校では冬の1月から2月頃に行なわれます。
専門学校では、分野によっては卒業と同時に資格が取得できるというケースもありますので、学校としてもむやみに進級をさせて簡単に卒業させては、学校の信頼を失うことになりかねません。そこで毎年、資格を得るにふさわしい力を身に付けているかを学力試験、実技試験などで見極めます。
進級の条件は専門学校によって様々です。試験の点数が基準点に達しない場合に進級を認めない学校や、順位で決める場合、試験の結果と日常の授業態度や課題作品、実技の評価、授業への出欠状況など様々な条件を加味して総合的に進級を決める学校などがあります。
学校によっては、進級試験の直前に1年間の学習を復習する意味でも、進級試験対策と題した授業を徹底的に行なうことも。専門学校生にとっても、資格取得が遅れるだけではなく、授業料が1年分余分にかかるという経済的負担が大きくなることもあり、1年の中でも最も緊張感を持って学習に臨む時期と言えるでしょう。
クリスマスにお正月などのイベントが目白押しの冬。製菓系の専門学校生の多くが目指しているパティシエにとっては一年でいちばん忙しい季節です。また料理の道を志す学生にとっては、年末年始の食文化は大いに勉強となることでしょう。さらにウエディング業界に関連する記念日にも注目です。
クリスマスケーキ

12月はパティシエが1年で最も忙しい時期。理由はもちろんクリスマスケーキです。クリスマスケーキとはクリスマスを祝って食べるケーキのことで、日本では1922年(大正11年)に不二家が初めて販売して広まったと言われています。スポンジケーキにホイップクリームなどを塗り、砂糖菓子のマジパンで作られたサンタクロースやクリスマスツリー、そして果物の苺などが飾られているのが定番です。最近では薪や木の切り株の形をした、フランスのブッシュ・ド・ノエルも定番となり、他にも有名なパティシエが趣向を凝らした物など毎年様々な種類のクリスマスケーキが登場します。
クリスマスケーキの受け取りは大体23日から25日に集中するため、短い期間に何百、店によっては何千というケーキを仕上げなければなりません。予約分だけでなく、当日購入に来るお客様もいるため店は膨大な忙しさに。この時期限定のスタッフを募集している店も多いので、パティシエを目指す学生にとっては経験を積む良いチャンスとなるでしょう。
年越しそばと年明けうどん
年末年始の食事として欠かせない物のひとつとして、大晦日の12月31日に縁起を担いで食べる年越しそばがあります。他の麺類よりも切れやすいそばにちなみ、今年一年の災厄を断ち切るという意味があります。基本は年越し前に食べますが、元旦に食べる地域もあるそうです。大晦日の蕎麦屋は通常よりも遅くまで営業して年越しそばをふるまっています。
そして、新しく誕生したのが年明けうどん。“うどん県”として知られる香川県にあるさぬきうどん振興協議会が推奨しています。定義として食べる期間は元旦の1月1日から15日までの間、純白のうどんに1点新春を祝う紅色の食材を用いること。純白で清楚なうどんを年の初めに食べることにより、その年の幸せを願う物だそうです。紅色の食材としては、梅干し、金時人参の天ぷら、えびの天ぷら、かまぼこなど。新しい年明けに紅白のうどんを食すことで華やかでめでたい気持ちが高まりそうです。
年末年始の江戸時代に定着した日本の風習である年越しそばと、新しい食文化となりそうな年明けうどん。料理の道を志す専門学生であれば、どちらもあわせて楽しみたいですね。
1月20日は「玉の輿(たまのこし)の日」
1月20日はウエディング業界に関する記念日があり、世の女性たちだけでなく男性たちも気になる「玉の輿」の日です。1905年(明治38年)、祇園の芸妓お雪がモルガン商会創始者の甥、ジョージ・モルガンと結婚したことが由来となっています。落籍料(芸者を稼業から身を引かせるための料金)は当時のお金で4万円、現在のお金で言うと4,000万円という莫大な金額でした。お雪は“日本のシンデレラ”と呼ばれ、彼女の半生は「モルガンお雪」として帝国劇場にてミュージカルとして上演されました。伝記としていくつか書籍も存在しています。
「玉の輿」とは、女性が金持ちの男性と結婚することで、自分も裕福な立場になることを言います。語源は、江戸時代、八百屋の娘だったお玉が三代将軍徳川家光の側室となり五代将軍綱吉を産み、従一位の高位にまで昇り詰めたお玉説などがあります。このお玉はのちの桂昌院であり、故郷の氏神である今宮神社の再興に貢献したことから、今宮神社は別名“玉の輿神社”と親しまれ、玉の輿を夢見る女性が全国から訪れています。
クリスマスやお正月など、冬はイベントも多い時期ですが、専門学校の最終学年は国家試験や卒業制作・卒業発表会の準備などで、忙しい時期となります。学校もそれに合わせてサポートをしたり、生徒の進路を考えたりと対応に追われます。また、この時期に専門学校に入学を希望する社会人のための入試を実施する学校もあり、人の動きが気ぜわしくなる時期です。
国家試験対策

春には医療系を中心に国家試験が多く行なわれます。専門学校の冬の期間は、授業の他に国家試験対策が中心となります。
国家試験対策で、筆記試験では、過去問題を分析して出題が予想される問題を解説したり、国家試験と同じ時間、問題数、マークシート方式での模擬試験を実施したり、弱点を克服するための補修講義などが行なわれます。医療系は、過去問題を重点的に、美容系は1月の実技試験、3月の筆記試験の対策が行なわれ、実技試験では試験会場などでカットやセットのポイントを復習します。また、調理師の場合は国家試験ではありませんが、各都道府県で調理師試験が実施されており、複数の都道府県でのかけもち受験も可能です。実施日は都道府県によって異なりますが、1~2月に行なうところもあり、筆記試験で合否が決まります。試験科目は7科目で1科目でも平均点を大きく下回ると不合格になることもあるため、知識が偏らないよう、苦手科目を克服することが合格への早道です。
国家試験は夢を実現するための第一関門。学校のサポート制度を最大限に利用して、国家試験を突破しましょう。
卒業制作・卒業発表会

アート系、ファッション系の専門学校ではこの時期、卒業制作や卒業発表会など卒業前の課題の準備に余念がありません。卒業制作や卒業発表会は、学校生活の集大成で、生徒たちも最後の課題とあって作品づくりに力を込めます。
デザインや写真、イラストレーションなどアート系の専門学校では、卒業制作の作品を展示して展覧会を開き、一般に公開します。企画から搬入・搬出、ポスターや案内ハガキなども生徒たちの手によるもので、父兄やデザイン関係者などいろいろな人が観覧にやってきます。生徒たちもこのときばかりは独創的で個性的な作品を展示し、有終の美を飾ります。
服飾、理容・美容などのファッション系の専門学校は、ファッションショーなどの発表会を開いて、独自のセンスをカタチにします。これも企画から演出、モデルなどを生徒たちがこなし、自分たちの世界観をアピールします。
社会人入試制度

専門学校は、社会人にも広く門戸を開いており、実際に多くの社会人出身者がキャンパスで学んでいます。大学を卒業して社会に出てからスキルアップが必要と感じた人や、転職のために資格取得を考えている人、好きなことに改めてチャレンジしようとする人など、いろいろな人が専門学校の門をたたいています。社会人を経験してから入学する人は、目的意識がはっきりしているので、学習に対してモチベーションが高く、理解や習得も早いとされています。
社会人を受け入れている専門学校は、社会人のための入試制度を設けており、入試が行なわれるのは冬の時期が多い傾向にあります。社会人入試では、推薦入試と同様に面接や論文などで選考することが多く、学校によっては新卒者とは違った選考方法を行なうところもあります。また、学費についても入学金や授業料の一部が免除されたり、低金利の学費ローンが利用できたりと、学校によって様々な優遇措置が用意されています。
仕事を続けながら専門学校に通いたい人には、夜間部の学科、通信制や単位制の学科で学ぶことができます。平成24年度から専門学校でも「通信制・単位制」が正規の専門課程の学科として認められるようになりました。eラーニングの普及もあって各分野で実施が拡大しています。
また、専門課程以外に資格試験対策などの短期集中コースを開設している専門学校も多く、自身の目的や都合に合わせて学校を選ぶことができます。この他にも社会人向けプログラムとして、厚生労働省の就職支援事業制度の認定を受けた講座や授業も専門学校で行なっています。条件によって受講料の一部が支給される「教育訓練給付制度」、受講料無料の上、要件を満たせば給付金が受けられる「求職者支援制度」があります。
このように一度社会に出た人でも、専門学校で新しい一歩を踏み出すことができます。









