専門学校情報
弁護士/ホームメイト

「弁護士」の仕事は、法廷(裁判)で依頼者の代理人または弁護人として弁護(主張)を行ない、依頼者の権利や利益を守ることです。なお、法廷(裁判)に入る前の示談交渉の他、法律相談、法律・法務関連の文書作成など、様々な法律事務処理も行ないます。弁護士になるためには、「司法試験」に合格しなければなりません。司法試験に合格後、司法修習を経て司法修習生考試をクリアすれば、弁護士の資格を得られます。
弁護士の資格
弁護士として活躍する分野やフィールド、仕事内容をはじめ資格を取得するための試験などをご紹介します。
弁護士になるまで

弁護士になるための〔第1ステップ〕は、法科大学院の卒業、あるいは司法試験予備試験の合格です。
法科大学院は全国各地の大学に設置されており、通常3年間の課程となります(入学試験で認められた者に限り、2年間の課程となります)。
〔第2ステップ〕は、「司法試験」の合格です。
司法試験は、大学院の終了(あるいは予備試験合格)後、5年以内に3回の範囲内でしか受験することができません。受験資格がなくなった者は、再び法科大学院を卒業するか、司法試験予備試験に合格すると、再び同条件にて司法試験の受験が認められます。
〔第3ステップ〕は、1年間の司法修習です。
司法試験の合格者は、最高裁判所に「司法修習生」として採用されます。司法修習生は、守秘義務・修習専念義務を負うため、副業やアルバイトは許されていません。司法修習の最後を締めくくるのは、国家試験「司法修習生考試」です。この試験に合格した者は、晴れて弁護士登録資格を得られます。
司法試験
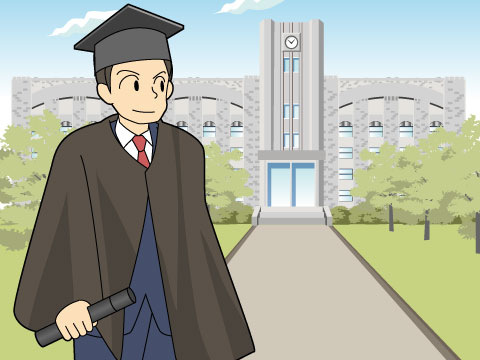
弁護士になるには、法務省の実施する国家試験「司法試験」に合格しなければなりません。司法試験は、毎年5月中旬から4日間行なわれ、以下のいずれかの条件を満たすと受験することができます。
受験資格
法科大学院課程の修了、あるいは司法試験予備試験(予備試験)の合格より5年間の期間内で、受験回数(3回)の範囲内である者。
試験科目

(1)短答式試験(公法系科目・民事系科目・刑事系科目)
(2)論文式試験(公法系科目・民事系科目・刑事系科目・選択科目※)
※倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法〔公法系・私法系〕の8科目から1科目を選択する。
試験日・合格発表
試験日:毎年5月中旬~下旬(4日間) / 合格発表:毎年9月中旬
試験会場
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市
申込方法
郵送によって申込み(出願)する場合、願書と必要書類を「司法試験委員会」宛てに郵送(書留)します。なお、願書の入手方法としては、①法科大学院を通じて交付を受けるか、②郵送、③来庁のいずれかとなります。
インターネットを利用して申込み(電子出願)する場合、法務省ホームページの「オンライン申請」から行ないます。
受験願書受付期間
毎年11月中旬~12月上旬(電子出願の場合は11月下旬)
受験手数料
28,000円(電子出願の場合は27,200円)
必要な物(一般的な例)
受験願書、顔写真(縦5㎝×横4㎝)、住民票。
合格率
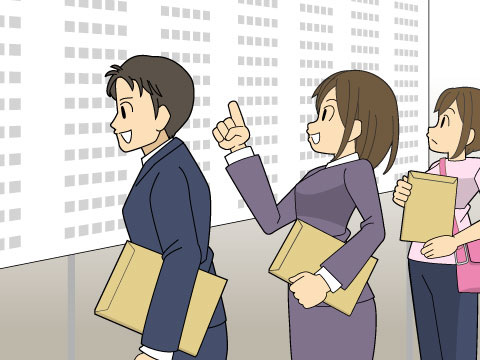
近年は、約25%の合格率となっています。
弁護士の仕事

弁護士は、民事訴訟において、原告あるいは被告の代理人として立証活動を行ないます。また、刑事訴訟においては、被告人の無罪や減刑のため、検察官と争います。
その他にも、自己破産や会社更生法の申請、民事上の法律問題における示談交渉など、様々な業務を行ないます。また、法律問題に悩みや問題を抱える人に対する法律相談も、主要業務のひとつです。
関連するその他の資格
法律・法務に関連するその他の資格をご紹介します。
司法試験の合格後、就任資格を得られる職業(弁護士以外)
- 裁判官
-
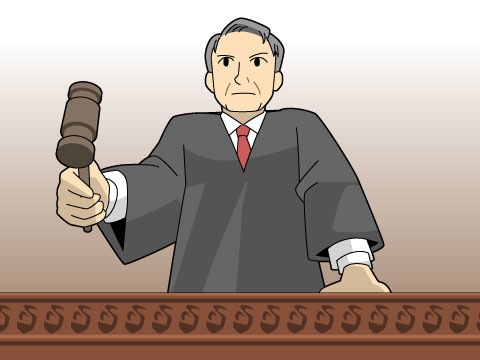
裁判官は、法廷において、紛争や事件を審理・裁判し、解決します。すべての権力から独立し、憲法・法律と良心にしたがい、独立な立場でその職権(法廷における審理)を行使します。
裁判官は国家公務員(特別職の)と位置づけられ、最高裁判所の裁判官(長官1名と判事14名)と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)の裁判官の2つに分けられます。最高裁判所の裁判官は10年毎に国民審査を受け、70歳で退官します。
- 検察官
-
検察官は、刑事事件の起訴・不起訴を判断、適当な刑罰を求刑し、裁判所において意見陳述などを行ない、弁護士と争います。
一般的に、「検事」とも呼ばれています。
弁護士であれば登録することができる職業(国家資格)
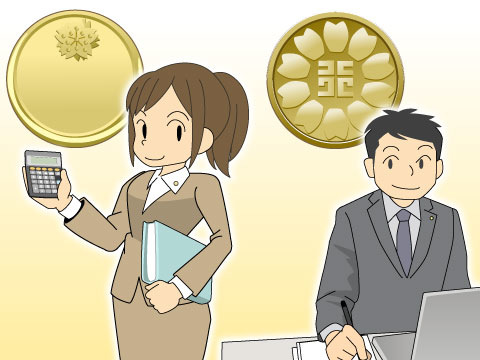
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 税理士
弁護士であれば一部の業務を行なうことができる職業(国家資格)

- 司法書士
- 海事代理士









