専門学校情報
弁理士/ホームメイト
「弁理士」とは、「特許権」「意匠権」「商標権」「実用新案権」の4つの産業財産権に関して事務手続きを行なうために必要な国家資格で、弁理士法によって規定されています。
依頼者の発明品や商標がすでに登録されていないかどうかの調査や特許庁への出願手続きなど、産業財産権にかかわるすべての事務手続きを行ないます。
弁理士の資格
弁理士として活躍する分野やフィールド、仕事内容をはじめ資格を取得するための試験などをご紹介します。
弁理士になるまで

弁理士になるためには「弁理士試験」に合格したあと、経済産業大臣から指定を受けた機関が実施する実務修習を終了し、弁理士登録をしなければなりません。
ただし、弁護士の資格保有者、及び特許庁の審査官あるいは審判官として通算7年以上、審判または審査の事務に従事した者については、弁理士試験に合格しなくても弁理士になることができます。
弁理士の仕事

弁理士の主な仕事には、発明品などにおける商標登録の状況調査や、特許庁への出願手続きがあります。特許や著作物に関する権利や、技術上の秘密の売買、ライセンスの契約など、企業間の契約交渉や代理での契約締結も認められているため、企業のコンサルティング業務全般を引き受ける場合もあります。 企業間の交渉は海外企業も対象となるため、日本国内だけでなく、世界を舞台に活躍できる仕事です。
また、弁護士と共同で代理人として民事訴訟をすることもできます(一部の訴訟に限定されます)。
弁理士試験
弁理士になるための「弁理士試験」は、毎年1回、工業所有権審議会によって実施される国家試験です。1次試験から3次試験まであります。
受験資格
学歴や年齢など、制限なし。
試験科目
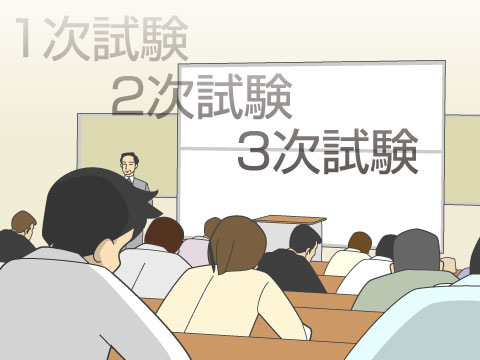
- 1次試験
- 短答式試験(産業財産権に関する法令・条約・著作権法・不正競争防止法)
- 2次試験
- 論文式試験(特許法・実用新案法・意匠法・商標法・選択科目※)
- ※理工Ⅰ(工学)、理工Ⅱ(数学・物理)、理工Ⅲ(化学)、理工Ⅳ(生物)、理工Ⅴ(情報)、法律の6科目から1科目を選択する。ただし、理系あるいは法学の修士号や一定の資格(技術士、一級建築士、薬剤師など)を有する者は、選択科目が免除となる。
- 3次試験
- 口述式試験(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)
- ※2次試験は1次試験の合格者、3次試験は2次試験の合格者のみが受験する。ただし、受験の前年またはその前の年の1次試験、あるいは2次試験の合格者についても、受験が認められる。
試験日・合格発表
- 1次試験
- 毎年5月中旬~下旬
- 1次試験合格発表
- 6月上旬~中旬
- 2次試験
- 必須科目は毎年6月下旬~7月上旬/選択科目は毎年7月下旬~8月上旬
- 2次試験合格発表
- 9月中旬~下旬
- 3次試験
- 毎年10月中旬~下旬
- 3次試験合格発表
- 毎年11月上旬~中旬
試験会場
- 1次試験
- 仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
- 2次試験
- 東京、大阪
- 3次試験
- 東京
申込方法
特許庁に受験願書を郵送します(郵送のみの受付)。
受験願書受付期間
毎年4月上旬
受験手数料
12,000円(特許印紙)
必要な物(一般的な例)
受験願書、顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)。
合格率
近年は、約10%弱の合格率となっています。









